盛り塩とは
盛り塩(もりじお)とは、家やお店、職場などに小さな円錐や山の形に塩を盛ることで、
場を清め、邪気を祓い、良い運気を呼び込むとされる日本の伝統的な風習です。
昔は中国の風習が日本に伝わり、特に「客を呼ぶ縁起担ぎ」として商家や料亭の玄関に置かれることが多くなりました。
盛り塩の効果
- 浄化作用:悪い気(邪気・穢れ)を吸収し、空間を清める。
- 商売繁盛:飲食店や店舗の入口に置くと「お客を呼ぶ」と言われる。
- 家庭円満:家の気を整えて、調和を保つ。
- 魔除け:玄関や鬼門に置いて、災いを遠ざける。
盛り塩のやり方
- 塩を用意する
- 天然の粗塩や精製されていない自然塩が望ましい。
- 形を整える
- 小皿や専用の盛り塩型を使って、円錐や三角錐に整える。
- 形を整えること自体が「心を整える」意味を持つ。
- 置き場所
- 家や店舗の玄関(内側または外側)。
- 飲食店では入り口の両脇に置くことが多い。
- 交換のタイミング
- 1週間に1回程度、または汚れたらすぐに交換。
- 毎日取り替えるのが理想。
注意事項
- 使い終わった塩は捨てる
→ 清めた塩は役目を終えているため、料理に再利用してはいけない。
→ 水に流すか、半紙に包んで捨てるのが一般的。 - 形や置き方にこだわりすぎない
→ 気持ちを込めて置くことが大切。完璧でなくても効果はある。 - 清潔さを保つ
→ 盛り塩が汚れたり、放置されたりすると逆効果になる。
※この文章はチャットGPTによって作成され、三田が一部加筆しています。
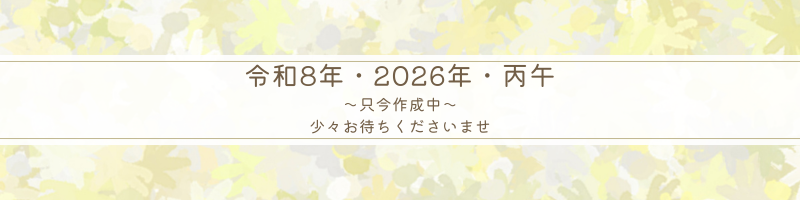

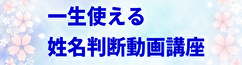

四柱推命が難しかった方へ